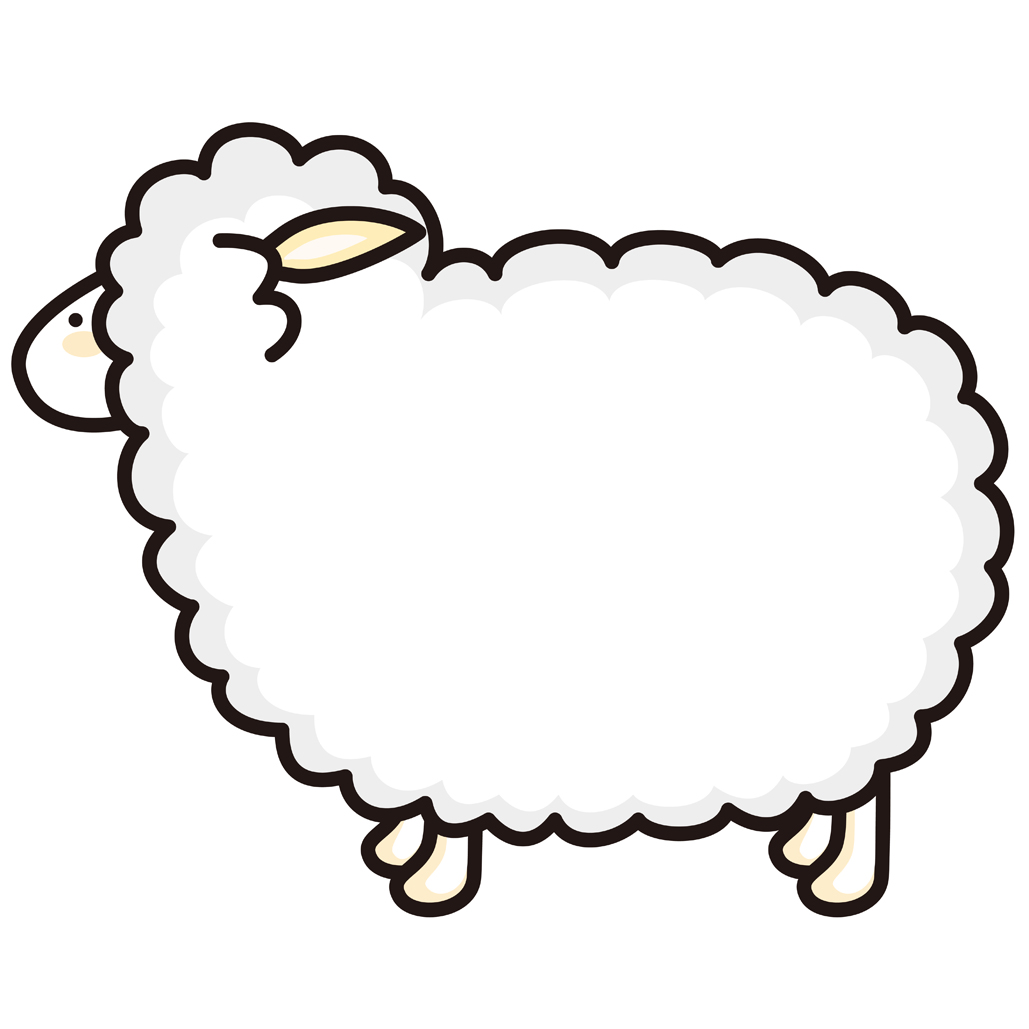プラトン『メノン』(385 BC?)
対話から想起へ
『メノン』は、プラトン初期対話篇の作品で、『ゴルギアス』とともに最も遅く書かれたと見られている。初期作と中期作の両方の特徴を持ち、中期への橋渡し的な位置付けにある。
主題となっていることは、「徳(アレテー)は教えることが可能なのか」という問いで、初期対話篇の『プロタゴラス』と同じ問題を巡って、対話が進められている。
『プロタゴラス』では、若きソクラテスが、老獪なソフィストのプロタゴラスに対して論争を挑むという対話形式だったが、『メノン』では、晩年のソクラテスが、10代の若き美少年メノンの質問に対して答えるという形をとっている。
対話の舞台は、およそ前402年頃のアテネ、ソクラテスは60代後半で、刑死する3年ほど前。『メノン』でのソクラテスは、議論の対話者としてよりも、若者を教え、導く立場の者として描かれている。
プラトンはなぜ、『プロタゴラス』と同じ主題を再び取り扱ったのか。そして、その対話の舞台として、最晩年のソクラテスを描いたのか。
それは、プラトン自身が、自らの思想を表現するために、指導者としてのソクラテス像を必要としたからではないだろうか。この時期、プラトンはソクラテス的対話の手法から脱却して、独自の思想を確立しつつあったと考えられている。
プラトンが『メノン』を執筆したのは、前388年のシケリアへの旅からの帰国以降で、シケリアでピュタゴラス派の強い影響を受けた後と推測されている。プラトンは、ピュタゴラス派から、存在論における観念論(Idealism)的思想を学んでいた。プラトンの代表的な思想である「想起説」はそこから着想を得たものだ。
プラトンは、『プロタゴラス』でソクラテスが提示した徳(アレテー)を巡る問いに対して、この想起説によって答えることができると確信しつつあったはずだ。そして、その説を説く役割として、若者を導く晩年のソクラテスの口を借りたのだろう。
そのため、『メノン』には、ソクラテスの対話的手法とプラトンの観念論的な議論の二つの観点、方法論から対話が進展する。極めて短い対話でありながら、二つの観点から議論が展開している。その結果、異なる論理が相互に展開し、議論の結論が最初の問いへと帰っていくという複雑な構造を取っていて、読者には読みづらい印象を与えている。
『メノン』を読み解く鍵は、ソクラテスの対話的手法が目指すものと、プラトンの想起説が証明しようとしているものとを明確に分けて考えていくことにあるだろう。
ソクラテスによる対話的方法論
ソクラテスの思想は、「無知の知」という言葉で代表されるように、言葉の定義や用法が曖昧なまま、中途半端な理解で議論を進めることを厳しく戒めるものだ。
第2章の冒頭でメノンはソクラテスに対して次のように述べている。
ソクラテス、わたしはあなたにお会いする以前から、あなたは自分で難問に悩み、他人をも難問に悩ますことしか、しない人だという話を聞いていました。現にいまも、あくまでわたし個人の印象ですが、あなたはわたしに、魔法をかけ魔術で欺いて、文字通り呪文をかけてしまいました。それでわたしは、こんなにもたくさんの難問に取り囲まれて、途方にくれています。
ソクラテスの対話という手法は、相手の説から矛盾を引き出し、言葉の意味や内容に関して、曖昧な理解しかしていないことを自覚させることにあった。ソクラテスによって、自らの無知を自覚させられたものは、言葉本来の意義に立ち帰って、自らの力で考え直していくことが要求された。ここに議論の導き手としてのソクラテスの真骨頂がある。
メノンとの対話においても、ソクラテスは、徳(アレテー)は教えられるのかという問いに対して、まず、徳(アレテー)とは何かというその本質に関しての問いを繰り返している。
プラトンの想起説
一方、プラトンの思想には、「無知の知」が入り込む余地は一切ない。プラトンにとっては、人は生まれながらにして、その魂において、すべてのことを知っているのだ。知らないと思っているのは、魂がそのことを忘れているだけであって、正しい導きによって、人は正しい知識を得ることができる。論理的な正しい順序を追うことで、自らの力だけで、正しい知識にたどり着くとこができるはずだというのが、プラトンの信念だった。
ソクラテスがメノンの従者のひとりである少年に幾何学の問いを答えさせる場面が登場する。
ソクラテスは、少年に一つの正方形を示し、その2倍の面積になる正方形を求めるように問う。少年は、ソクラテスの説明に従って、元の正方形の対角線を一辺とする正方形から2倍の面積の正方形が求められることを「知る」。
少年は、この時、自らが今まで知らなかったことを知ったのである。自らの「無知」を自覚したのではなく、自らの「知」を自覚したのだ。
この幾何学の例えは、人間の知性の本質をきわめて鮮やかに描き出している。現代風に言えば、これは人間が生まれながらに持っている論理的思考能力の証明ということになるだろう。
プラトンはこれを「想起説」として体系化し、人間の知性の探究の手法をソクラテスの対話的方法論から大きく変えていくことになる。
この説を踏まえた上で、プラトンは、人が知らないと考えているものを探究すべきことが需要であること、そして、そのためには「仮説」を立てて論じるのが有効であることをソクラテスに語らせている。
結論としてのアポリア
さて。
では、もともとの問いであった「徳(アレテー)は教えることができるのか」という問題に対して、二人の対話の結論はどうなったか。
ソクラテスは、仮説を立てることの重要性を幾何学者が補助線を立て考察することに例えている。
そこでソクラテスは、徳(アレテー)は、有益なものでなければならない、という仮説から出発し、徳(アレテー)が有益であるためには、知性が伴っていなければならない、そして、徳(アレテー)が知性であるならば、教えることができる、という結論を導き出す。
だが、ここでソクラテスは、アニュトスとの議論から、優れたアレテーを持つものが、アレテーを教えることに成功することがないという反証を提示する。
そこでこの問いは、再び難問(アポリア)へと帰着する。ソクラテスは、仮説と反証によって問いを再び議論の始めへと戻し、言葉の厳密な意味から問い直すことを説く。「徳(アレテー)は教えることができるのか」という当初の問いは、結論に至らないまま、問いだけが循環して、対話の終焉を迎えることになった。
こうして『メノン』は、初期対話篇の形式を踏襲して、問いを読者に投げかかたまま終わる。
この対話篇では、想起と仮説による演繹的な論理的思考(プラトン)と、言葉の厳密な意味と定義を問う対話的手法(ソクラテス)が同時に示されている。この段階ではプラトンはまだ、想起のみによってすべての知識を正当化しようとはしていない。プラトンはこの『メノン』を出発点として、想起説を発展させ、独自の思想を築いていく。
『メノン』は、プラトンの思想形成を追う上でも、初期と中期の思想を結び付ける上でも極めて需要な作品だ。そしてまた、「教育は可能か」「知性はどのように獲得されるのか」という人間の本質を巡る問いを投げかけてくる作品でもある。