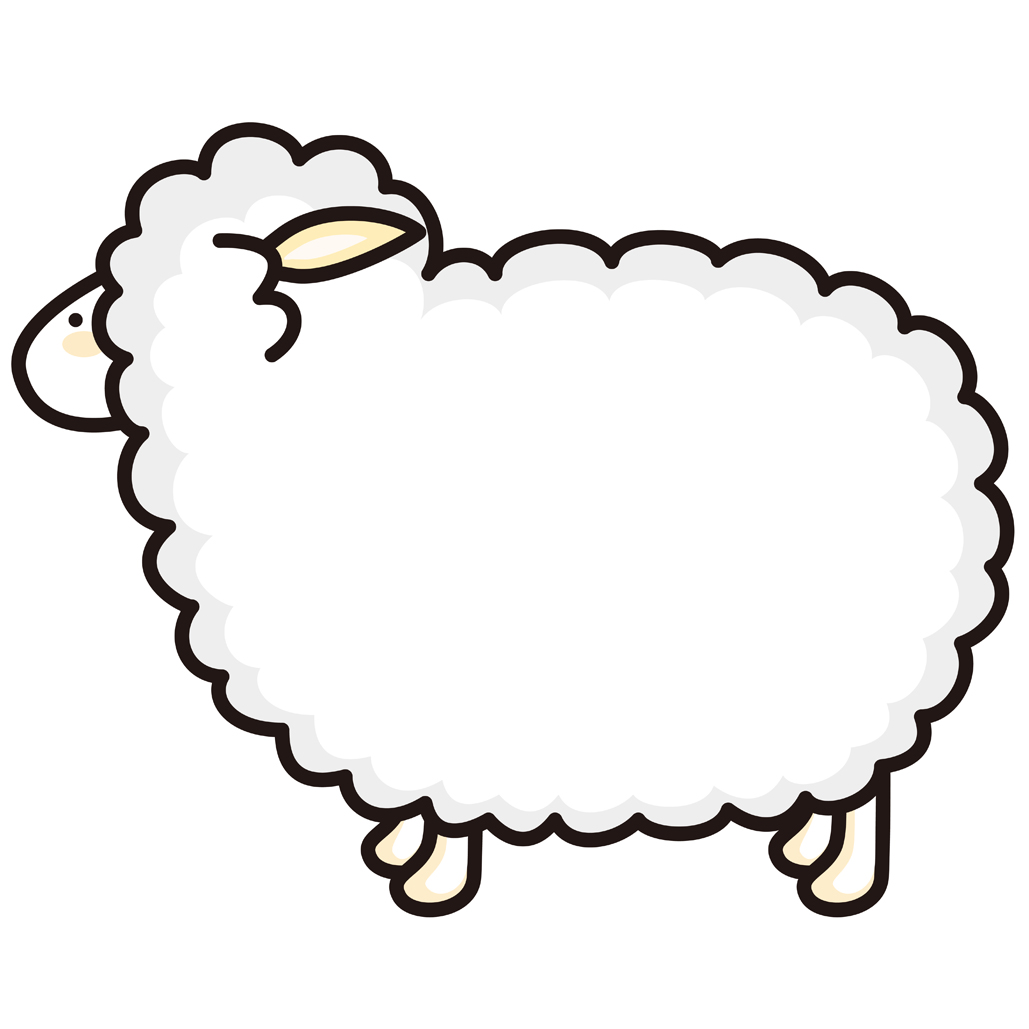デカルト『情念論』(1649)

受難、受動、情念
ラテン語の語源から言うと、ヨーロッパ諸言語のpassionという言葉は、「受難・苦しみ」という意味から来ている。苦しみを受けるという体験が、「受動(passion)」という意味になり、さらにその経験から引き起こされる激しい感情から、「情念(passion)」という意味にまで広がった。
その語源が示すとおり、西欧では、情念(passion)は、精神が被る激しい体験によって、引き起こされるものとして理解されている。つまり、外部に対する精神の反応こそが感情なのだ。感情は、精神が外部からの影響を受け、その反応として表現される。
したがって、デカルトの『情念論』は、精神が外部からの影響によって得る経験についての論考だといえる。『情念論』(原題: Les Passions de l’âme)は、「精神の受動」と訳すこともできる。このpassionという言葉が持つもう一つの意味、「受動」からも推察されるように、精神が外部からの影響を受けること、すなわち「受動」の経験によって、どのような心理状態が生ずるかを考察したものだ。
精神の表現である感情を外部からの影響による反応として捉える辺りに、機械論的な発想を精神の領域にまで拡張しようとするデカルトの科学的な態度が窺える。
精神の働きである感情は、捕らえ所のない不可解なものではなく、外部からの影響によって、科学的な因果関係の下で把握できるものになる。このような観点から感情を捉えようとする態度は、やはり非常に近代的なものだ。
デカルトは、この情念論を展開するに当たって、当時の科学的な知識を広範に援用している。ハーヴェイの血液循環論(1628)など、当時の最新の説が参照されている。
感情についての演繹的考察
デカルトは、精神の受動として感情があるのだとすれば、その精神に能動的に働きかける主体があるはずであり、それは身体でしかありえないと言う。能動的主体としての身体は、精神に影響を与える起因として捉えられている。そこで、精神と身体の峻別が感情を理解する上での前提となる。
精神に帰属するものを身体に帰属するものから周到に峻別した上で、その前提から理論を組み立てていこうとする姿勢には、デカルトの心身二元論的な特徴がよく表れている。
しかし、精神と身体を区別する根拠としての受動と能動という区別は、同じ一つの出来事を二つの異なる側面から眺めたものでしかない。したがって、デカルトの心身二元論においても精神と身体は、相互作用のあるものとして一体のものとして考えられていることは、注意しておくべきことだろう。
デカルトは、身体を感情の起因になるものとして精神から区分した上で、感情の起因となるものをさらに細かく区分していく。
身体に直接関係付けられる知覚は、飢え、渇きといったその他自然的な欲求であり、その他に、痛み、熱さなど、外部の対象に起因するものが含まれる。
それに対し、精神だけに関係付けられる知覚は、喜び、怒り、悲しみなどの感覚である。これらの感覚は、デカルトが本書の議題としようとしている、この狭い意味での諸情念passionsであり、これは、デカルトの言う動物精気に由来する意思とも区別されるという。
この動物精気というものは、今で言うところの神経伝達物質のシナプスのようなものを想像すれば、理解しやすいかもしれない。デカルトの理解によれば、動物精気は脳の松果腺に由来し、神経を通じて身体を動かし、人間の意志を司るものとされている。
当時の人間の身体の働きに関する知識は、主に解剖学からのみだったことを考えると、そこまで推論を働かせていたことに驚かされるが、この動物精気という考えは、デカルト以降は忘れ去られていく。動物精気は、歴史から忘れ去られた説だが、神経伝達物質として理解すれば、決して的外れな推論を行っていたわけではないことが理解されるだろう。
しかし、この動物精気は、人間の意志に関わるものであるから、デカルトは本書の情念に関する議論からは外れるとしている。
こうして純粋な意味での精神的な「情念」が議論の対象として取り出される。ここには、疑い得ない議論の前提までさかのぼって、そこから演繹的に議論を組み立てていこうとするデカルト的な思考法を窺うことができる。
本書の二部では、こうして純粋に取り出された人間のさまざまな感情について、一つずつその性格が論じられていく。道徳を科学的に議論しようとする近代性が感じられる。
また、デカルトの感情に関する洞察は、今読んでも興味深いものが多い。17世紀の道徳論を垣間見ることができるだろう。
感情に対する捉え方の日本と西欧の差
デカルトの情念に関する議論を見ていくと、西欧語と日本語との間の「感情」の捉え方について大きな隔たりがあることに気付かされる。
日本人は伝統的に、感情というものは、自分の内から自然と沸いてくるものと考えられているように思う。
日本語の感情に関する表現は、そのほとんどが自動詞、形容詞によるもので、感情は自分の中から自然と湧き上がってくるものとして表現されている。
「喜ぶ」「悲しむ」といったこれらの表現は、すべて自動詞だ。つまり、感情とは自分自身に起因していて、自然と沸いてくるものなのだ。他からの影響というものを特に意識せずに表現することができる。
だが、西欧語では、感情は主に他動詞で表現される。他動詞による表現は、感情が外部の要因によって引き起こされるものということを強く意識させる。
たとえば英語であれば、enjoy、disappoint、attract、interestなどの単語は他動詞であり、その本来の意味を忠実に訳せば、それぞれ、「enjoy 楽しませる」、「disappoint 落胆させる」、「attract 引き付ける」、「interest 興味を引かせる」、というようになる。
disappointed、interestedといった言葉も、現在では形容詞として解釈されるのが一般的だが、元は他動詞の受動態から来ている。
嬉しいのも悲しいのも、本来何か理由があるから、嬉しかったり、悲しかったりするのであって、何か原因が外部にあって、それによって自分の中にさまざまな感情が引き起こされると考えるのは、ごく自然のことだろう。だが、日本人は、理由は分からないが、なぜか自然と悲しい、嬉しい、といった「もののあわれ」「ものがなし」といった感情を重視してきた。
これは、感情に関する西欧とはまた違った見方を与えるだろう。
日本人には、日本人の『情念論』が必要なのかもしれない。