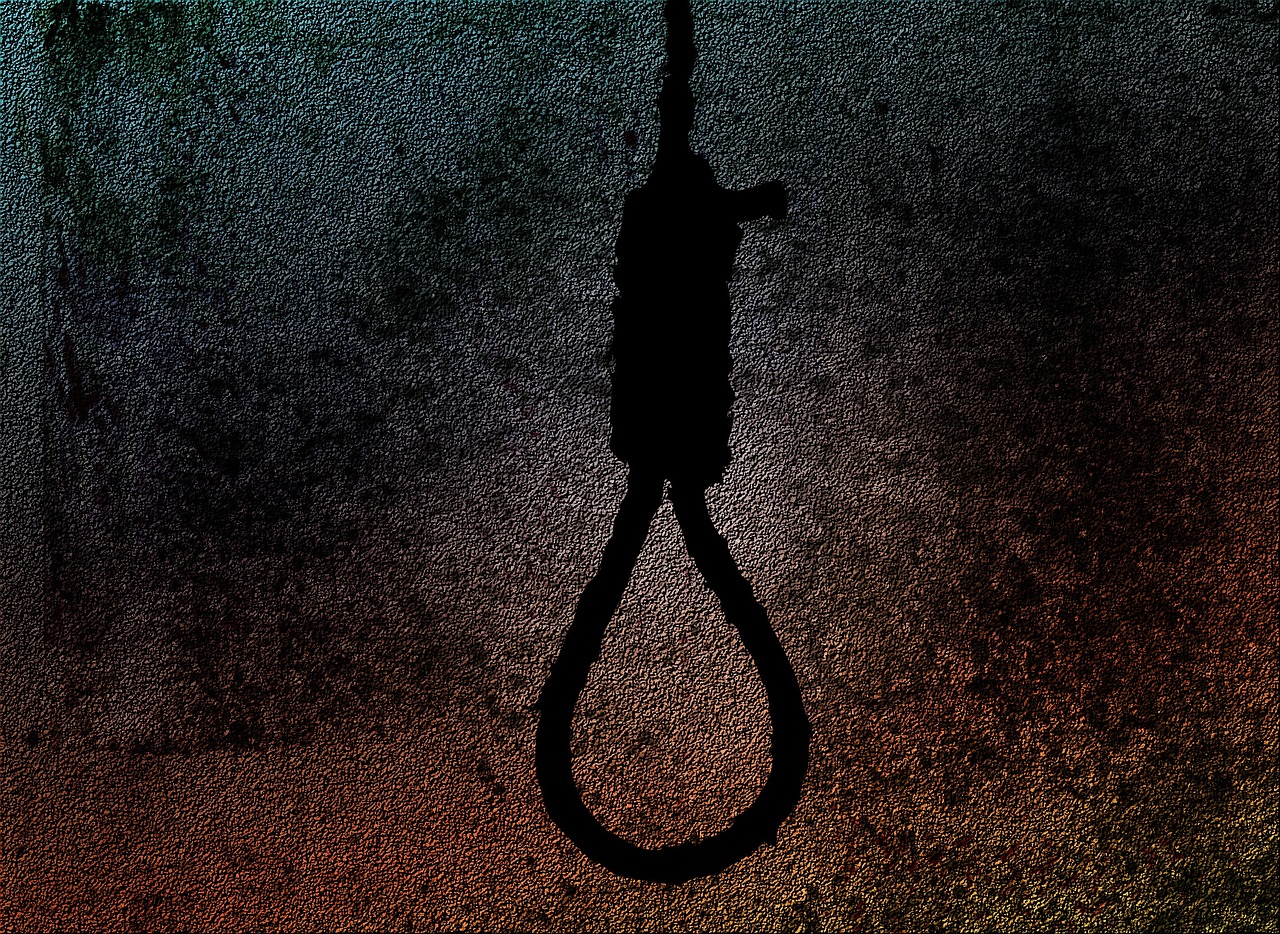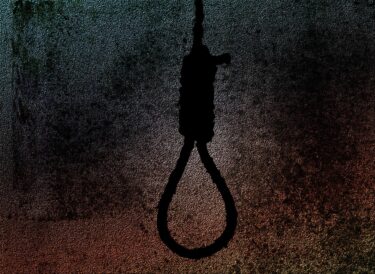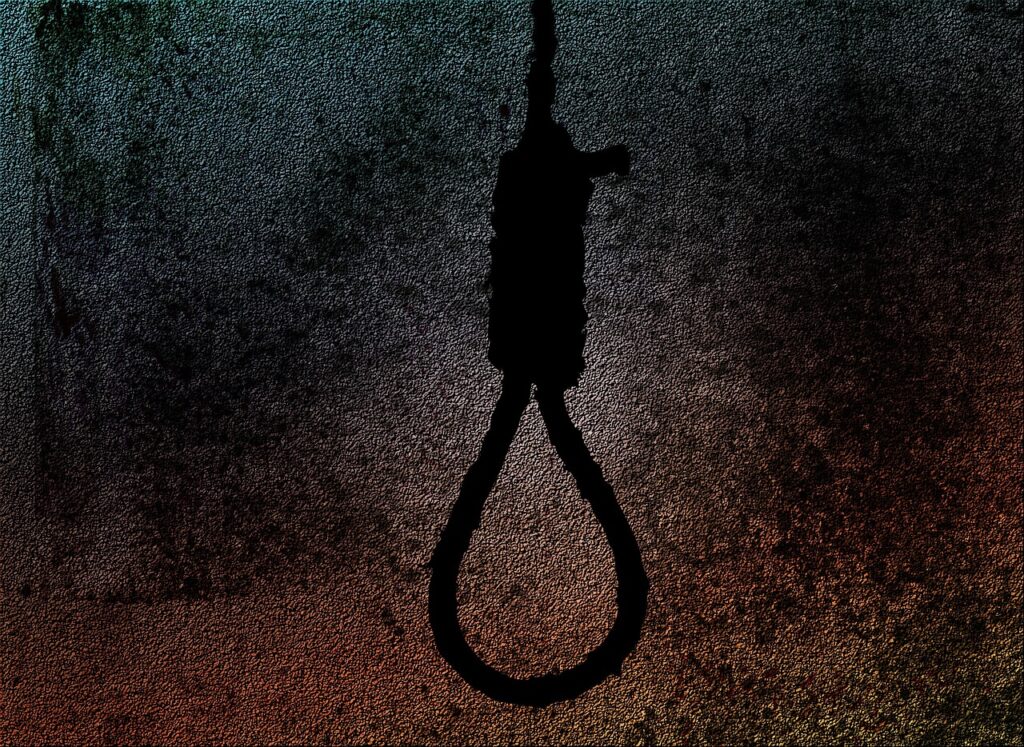
阿部謹也『刑吏の社会史』(1978)
社会史とは何か
社会史とは何を対象にした歴史なのだろう?
歴史学の中でも政治史、経済史、法制度史、美術史、建築史といったものは、対象がはっきりしているので分かりやすい。しかし、社会史と言われると何をする学問なのか途端に分からなくなる。
この分かりにくさの由来は、社会史が「歴史の全体像」を追及するところから生じている。
民衆の歴史へ
従来の歴史学は政治史が中心であり、権力者の推移や政権の興亡を描いてきた。
それに対して、社会史は、伝統的な歴史学から無視された一般民衆の歴史を描こうとする試みから始まった。そのため、もともと社会的に疎外された少数派や辺境者への親和性が高い学問だった。
民衆や下層へ追いやられた人々については、文献資料がほとんどない。歴史的な事件や権力者の移り変わりについては、当時の人々にとっても重要な出来事と意識されるため、記録に残そうとする動機が強く働く。
だが、一般の人々の暮らしというのは、注目されず人々の意識にも重要なものと映らないため、記録に残らない。そして時代が移り変わると、過去の人々がどのような暮らしを送っていたのか全く分からなくなる。
社会史は、そうした歴史から埋もれた権力者以外の一般の人々の歴史を文献資料以外のものをも用いながら再現しようとする学問だ。
刑吏の姿から見た西欧中世の世界像
著者の阿部謹也氏は、一般の人々の中でも特に社会的に疎外された人々への暮らしに多くの視線を注いでいる。社会的に疎外された被差別民を主な研究対象にしている。そして、そうした被差別民を生んだ社会的背景や差別意識を生んだ当時の人々の世界観や価値意識までを明らかにしていく。
本書での主題も中世ヨーロッパで差別された職業民、刑吏の歴史だ。刑吏の生活の実態を通して、当時の人々の世界観までを明らかにしていく。
本書の魅力は、被差別民の姿を通じて、当時の人々の世界観が再構成されていくところにあるだろう。刑吏の歴史そのものではなく、むしろそこから当時の人々の価値観を再構成するところに社会史としての面白さがある。
社会史における歴史の全体像とは、まさに当時の人々が共有していた世界像を明らかにすることで見えてくるようになる。文献的に確証できることだけを描くのが歴史だとしたら、社会史はそこから人々の世界観までを再構成する歴史学だ。
阿部謹也氏の『刑吏の社会史』はその意味で一級の社会史だろう。阿部氏は本書で、刑吏の歴史を通じて被差別民が登場した背景と差別という観念を生み出した当時の人々の世界観を明らかにしようとしている。
刑吏たちの世界の変遷
中世のゲルマン社会では、犯罪は共同体の紐帯や世界秩序の毀損と捉えられていた。したがって刑罰はその毀損を埋め合わせるための祭祀として考えられていた。
それが12世紀から13世紀にかけて貨幣経済が浸透し、都市が形成されてくるようになると、刑罰も個人の行為に対する罰則へと移り変わっていく。刑罰から祭祀としての性格が消えていくと、刑罰を担う刑吏は、権力と不浄な行為の象徴となり、賤民として位置づけられるようになる。
古代の共同体が崩壊し、都市という合理的な人間関係を要求する場が登場した。しかし、死や刑罰といった人々の紐帯を毀損させる合理化され得ない部分は、自らとは関係のないものとして、その関係性から排除する必要があった。
都市における合理化から排除された部分を担ったのが中世における刑吏や皮剥ぎであり、それが差別を生み出す背景となった。都市民は、彼らを差別することにおいて自らの合理性を保ったのである。
なぜ差別が生まれたのか、なぜ被差別民が必要とされたのかが、刑吏の歴史を通じて明らかにされていく。人々の観念や価値意識といった文献資料に残らないものを、被差別民の歴史から読み解いていこうとする手法は非常に鮮やかだ。
歴史の暗部に焦点を当てた著作だが、読んでいて興味の尽きない本。